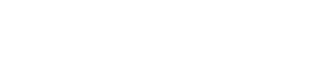製本の種類
上製本
本文と別仕立ての厚い表紙(ハードカバー)でくるんで製本
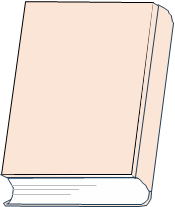
並製本
中身と表紙を同時にくるみ、三方を仕上げ裁ちした製本
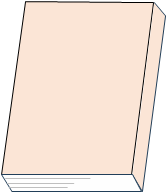
背
上製本=角背・丸背
並製本=角背のみ
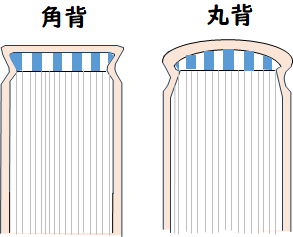
綴じ方
無線綴じ
背に当たる部分をのり付けし、表紙を貼り付ける
ページをバラバラにしてから接着する
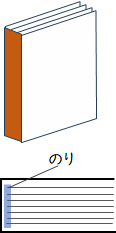
アジロ綴じ
無線綴じを改良した綴じ方法
オフセット印刷で製作する上製本の主流な綴じ方法の一つ
ミシン目状のスリットを入れ接着剤を浸透させる
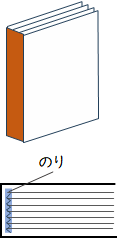
中綴じ
2つ折りにした用紙の中心を針金(ホチキス)で綴じて製本

平綴じ
重ね合わせた用紙の背の近くを、針金(ステープラ)などで綴じる製本

糸かがり綴じ
糸を使って本を綴じる伝統的な上製本の綴じ方
厚い本に対応でき、製本強度が強く、大きく開いてもページが脱落しないことが最大のメリット

ミシン綴じ
本の中心を糸で綴じる
薄い本(20枚程度)、見開きページなどにおすすめ

スクラム製本
中綴じと同様、2つ折りにした用紙を重ね合わせてまとめ、針金や糸などで綴じない

本の部位
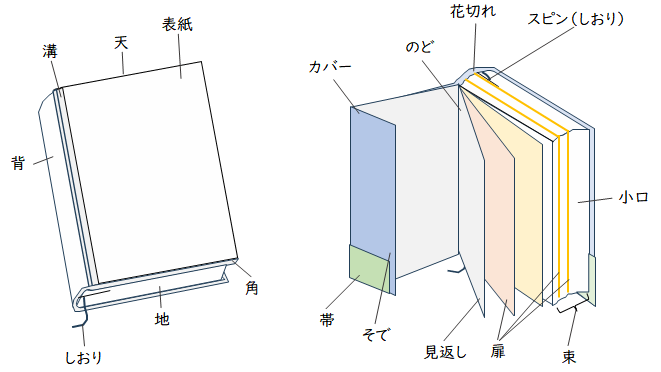
天
本の上の部分
地
本の下の部分
表紙
書籍本体の一番外側の部分
溝
表紙の両面、背の近くに刻まれている文字通りの「溝」で、本を開きやすくするための加工
背
本を綴じてある部分で本の背中、外側
カバー
表紙を覆うようにかけられる紙 本の印象を決める役割が大きく、デザインや質感にこだわりが求められる場合が多い 「ジャケット」とも呼ぶ
帯
表紙の上に巻く細い紙、通称「腹巻き」 本のキャッチコピーや推薦文など宣伝文句を書く 書店に流通させる場合には必要
そで
カバーや帯をかける時に、表紙の内側に折り込む部分
小口(こぐち)
本を開く側(背の反対側)
束(つか)
本の厚さのこと 「束幅」とも言う
のど
本を綴じている側、小口の反対部分
見返し
表紙と本の中身を接着するために用いられる紙 一般的には表紙や本文とは違う色の紙が使用されることが多い 表紙にくっついている側を「効き紙」、くっついていない側を「遊び」と言う
扉
本の内容がいくつかの部分に分かれている時に、その区切りとして入れられるページ
花切れ(はなぎれ)
背の接着面に貼り付けた布、「花布」とも書く 元は補強のために付けられていたものだが、現在は主に装飾用で付けられる
しおり(スピン)
布製のしおり 花切れと背の間に糊付けされている 「スピン」とは英語ではなく日本独特の呼び方で、英語ではブックマークまたはブックマーカー
本文の部位
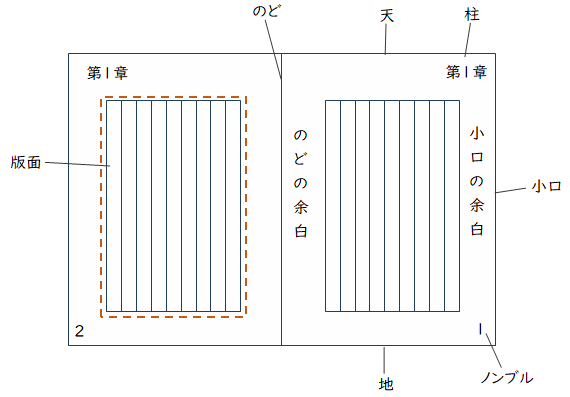
版面
本文が印刷される範囲 (はんづら・はんめん)
柱
章題や短編の題名などを表示 レイアウト位置は天地いずれでもかまわなく、小口側に置くこともある
ノンブル
ページを表示 「番号」という意味のフランス語で、柱同様、レイアウト位置は様々
キャプション
写真や図版を掲載するときは、必ず解説文を付記するようにする
字間
文字と文字の間隔 通常は活字の大きさそのままに並べる「ベタ組」にする 句集や詩集などでは活字と活字の間をわざと空けて、読みやすくすることもある
行間
行と行の間 通常の組版では、文字の大きさの半分(半角)以上の空き幅にする
段
通常は1段ですが、原稿の量によっては、2段組や3段組にすることもある
段間
2段組以上にする時の、段と段の間 通常は2文字分以上空ける